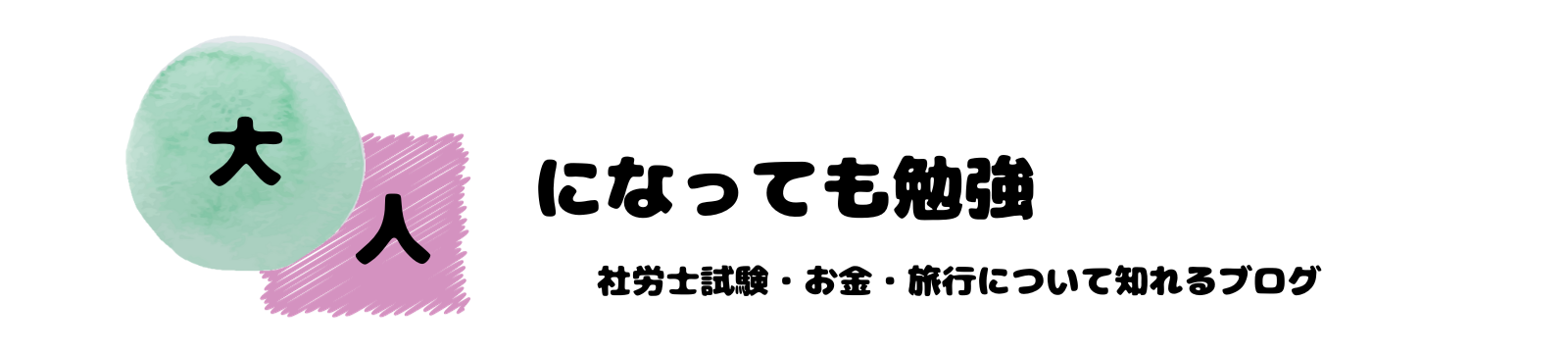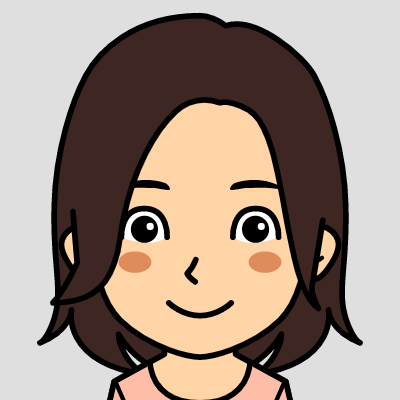
過去問を制するものが試験を制する!といわれるほど大切な過去問。
今回はどのように私が解いていたのかご紹介します。
解けない衝撃
講義も聞き、チェックテストも解き、そこそこ覚えたんではないかと思って過去問に取り組むと…
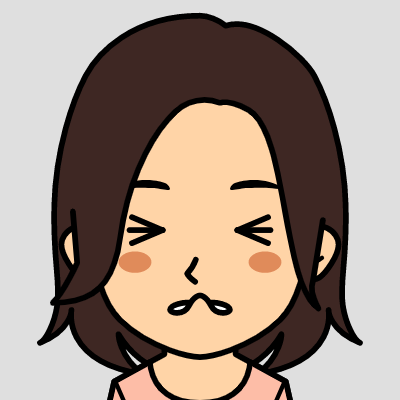
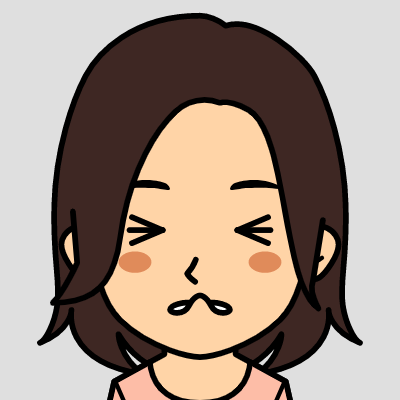
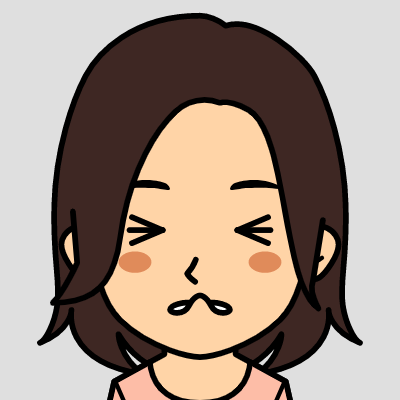
全く解けない…
という現実ぶち当たります。
そもそも、問題文も文章が長すぎて何を問いただしているのかさえ分からないという。
でも当然なので、落ち込むことではありません。だって、過去問という事はもともと本試験の問題だったという事。
学び始めでスラスラと解けるわけがないです。
と、いう訳で時間をかけて過去問は取り組むことが大切です。
👇私が使用していた過去問はこちらの通信講座
👇独学時代の市販の過去問
<労働保険編>
<社会保険編>
過去問との向き合い方
まずは問題の意味を理解する
択一式問題を解くときは選択肢それぞれの正誤判断をしますが、何を言っているのか分からない時は、その都度テキストに戻って確認します。
確認する時、前後の法律の関連する部分も一緒に把握しておくと、流れもつかむことができます。
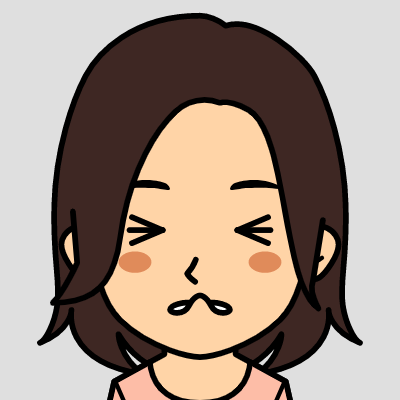
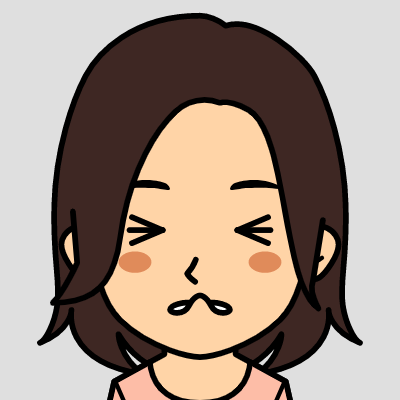
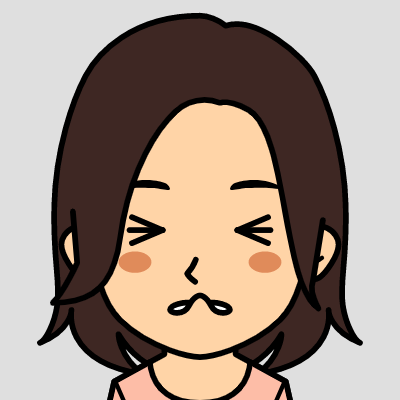
時間はかかりますが、分からないまま進むと似たような法律がたくさんあるので、後々混乱してしまいます…
答えがなんだったかなんて気にしない
A~Eの中から正しい(誤っている)ものを選べ。
なんていう形で出題するのがスタンダードな問題です。
「Aが正解!」という風に解答を導きだすのではなく、A~Eそれぞれの正誤判断が出来ているかを確認します。
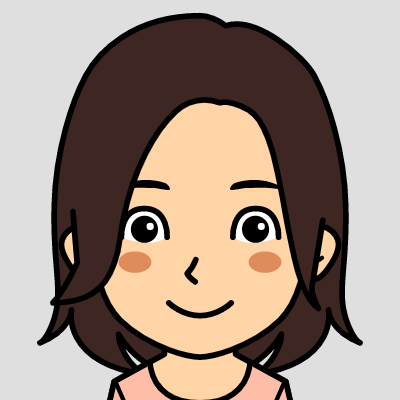
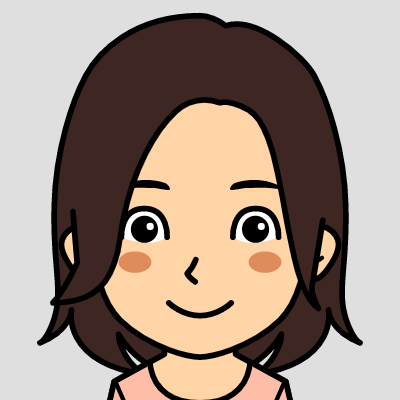
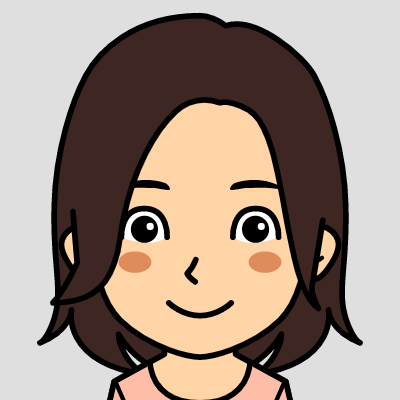
過去問は正解数を増やすものではなく、知識定着のために使用するのがポイントです。
私がやった過去問の解き方
1問を5問にする
先ほど、解答は気にしないといいましたが、もう少し詳しく記します。
A~Eを全て分解して考えます。もしすぐに「Aが答えだ!!」と分かってもきちんとEまで問題を解くのです。
例えば…A~Eの中で誤っているものを選択せよという問題だった場合、ノートにこう書きます。
- A × 日数が異なるから
- B 〇
- C 〇
- D 〇
- E 〇
逆に、A~Eで正しいものを選択せよの場合は、
- A 〇
- B × 対象になる
- C × 全てではない
- D × 都道府県知事
- E × 翌日
こんな感じで書きます。
もし、Aが正解だから先に進んでしまえ~としてしまうと、得られる情報が5分の1になります。
×だとわかっても、理由を間違えている場合もあります。
そしたら、違う問題の出題のされ方をされたら太刀打ちできません。
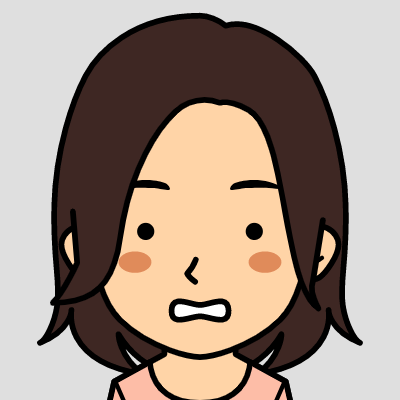
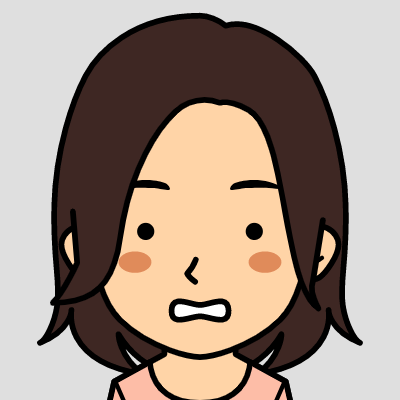
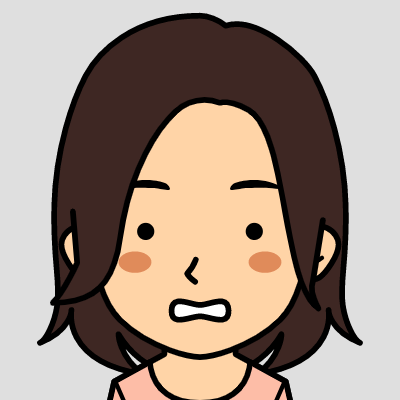
私は理由を誤っていたら、例え問題に正解していたとしても△として扱って、まだ理解できていないという事にしていました。
1問1答で解ける私が独学時代に使用していた過去問はこちら👇
<その①>
<その②>
<その③>
<その④>
とにかく繰り返す
過去問は何周も繰り返しました。もはや答えを覚えてしまうくらい繰り返します。
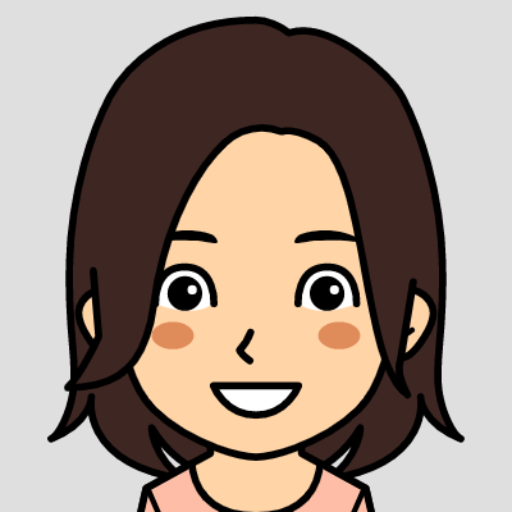
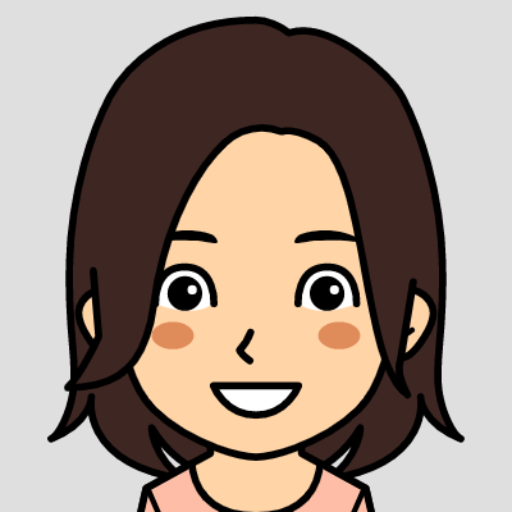
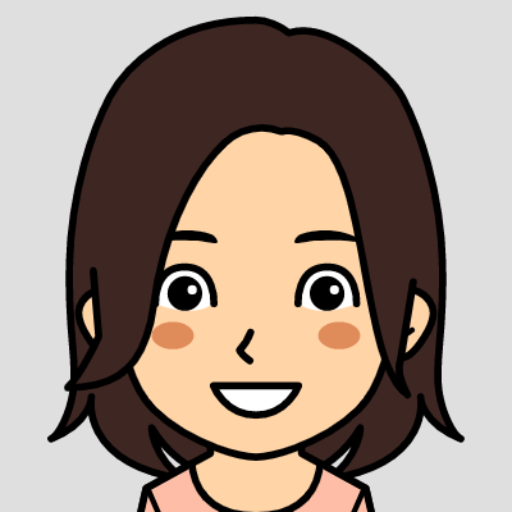
たくさんの問題集を購入するより、過去問をやりこむ方をオススメします。
答えを暗記するなんて意味あるのかな?と思われますが、暗記できるくらいやりこんでいれば、法律も暗記できるという事ですから。
細かい法律や判例を暗記するより、過去問で狙われがちな部分を暗記した方がずっと効率的だと思います。
試験は満点をとらなくても合格できます。あくまで、7割以上を目指せばよいのです。
そのためには、基本的なことを問いただしている問題を落とさないこと。これが大事です。
👇社会保険労務士試験の通信講座
【フォーサイト】
【クレアール】
【アガルートアカデミー】
まとめ
社会保険労務士試験の肝となる過去問について記しました。
テキストや過去問は、各通信講座で研究に研究を重ねて作成されています。
色々な特徴があるので、是非見てみてください。