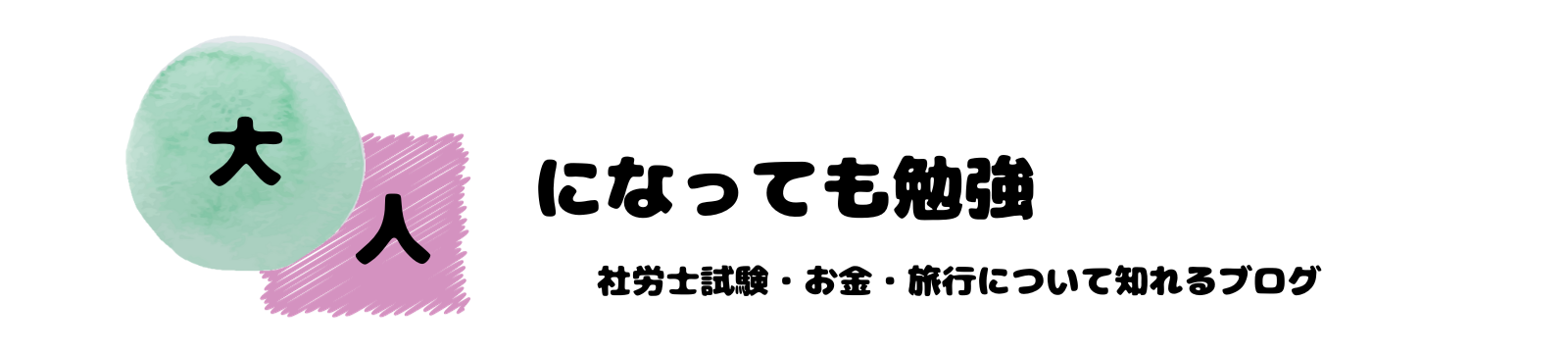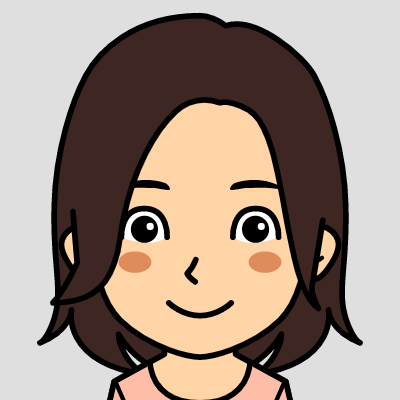
今回は社労士の実務についてお話しします。


お仕事の相手はだれか
基本的に、企業の代表取締役や総務人事部の担当の方とやり取りをします。
大企業だと社内の人事部内に社労士資格を有する人がいる場合が多いため、基本的に開業社労士が顧問先とするのは中小企業が相手のことが多いです。
社労士の実務
①諸手続き業務
最も基本的な業務としては、労災保険・雇用保険・社会保険の手続きです。
従業員が入退社したとき、雇用保険と社会保険を加入又は喪失させなければなりません。
健康保険証の取得や離職票の発行などが遅れないように手続きをします。
そういった随時行う業務以外にも、毎年7月に手続きを行う労働保険年度更新手続きや社会保険の算定基礎届手続きを行います。
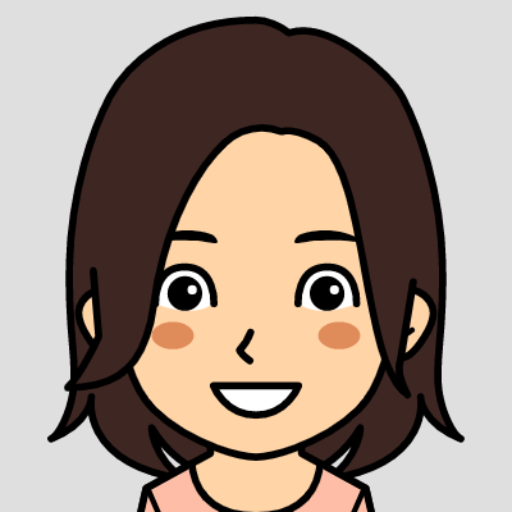
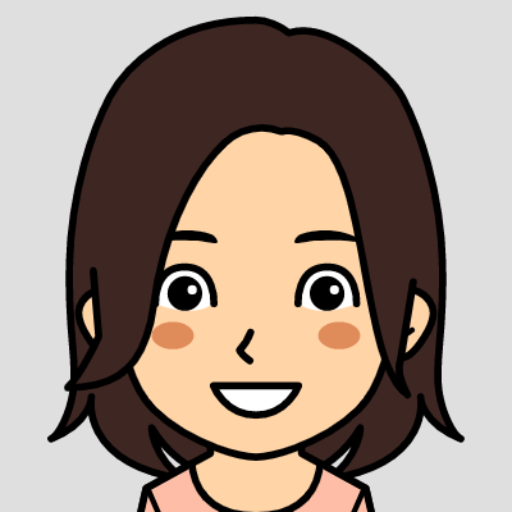
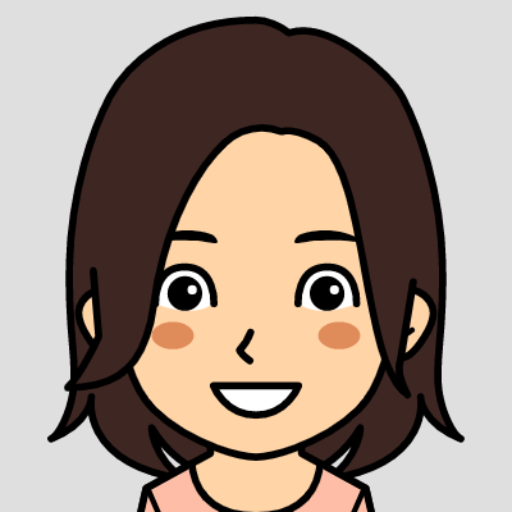
7月前後は社労士の繁忙期になります。
他にも、そもそも労災保険にも加入していない企業が新規で設立したいと言われた場合には、労災保険・雇用保険・社会保険の新規設立手続きを一から行います。
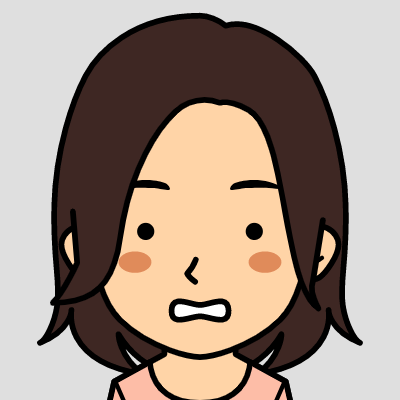
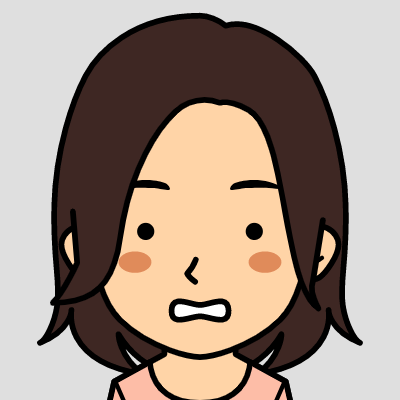
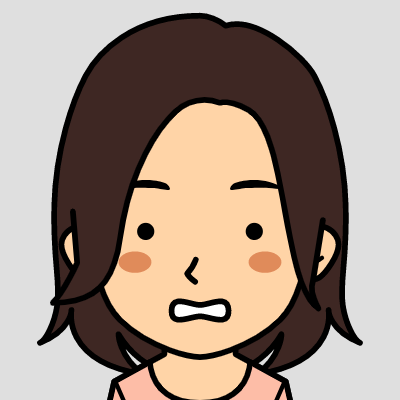
手続きの種類は今あげたもの以外にもたくさんあるので、その都度ケースバイケースで行っていきます。
とにかくたくさんの手続きを行うため、最近では電子申請で行う社労士さんが多いです。
その都度、紙で手続きしていたら膨大な時間がかかってしまいますからね…
②給与計算業務
え?給与計算って税理士がメインじゃないの?と思いますよね。私もそう思っていました。
実は、社労士も給与計算を行うことが多いです。
給与における控除欄には社労士の専門である「雇用保険料」「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」があるため、給与計算をお願いされることが多いのです。
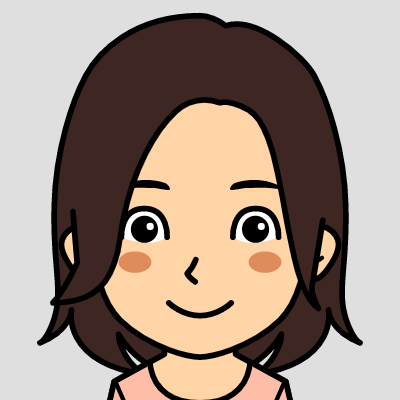
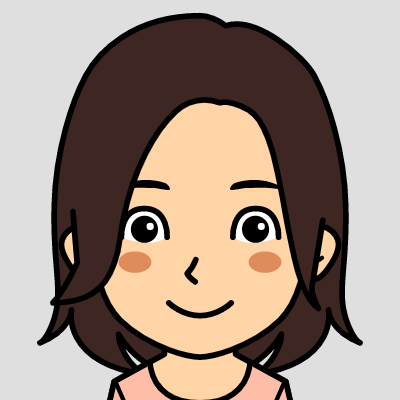
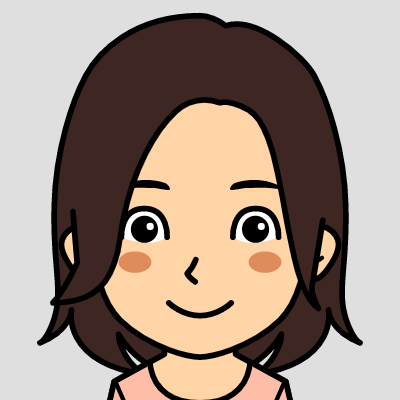
その代わり、所得税など税理士の範囲についても理解する必要があります。
③コンサルティング業務
顧問先での労働者とのトラブルや、今後の採用についてなど、顧問先企業が円滑に経営できるように人事関連の相談に乗ってお手伝いをします。
また、パワハラ防止法という法律が義務化され、各企業がパワハラの相談窓口を設置しなければならなくなりました。
そのため、社労士が窓口を担ったりすることもあります。
④助成金申請
厚生労働省が行っている助成金の専門は、社労士となっています。
労働者がよりよく働ける環境を整えた企業には助成金が交付されるのですが、申請がなかなか大変です。
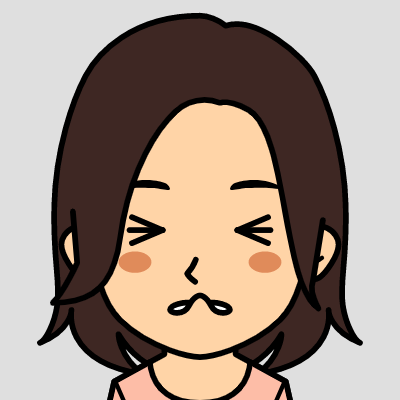
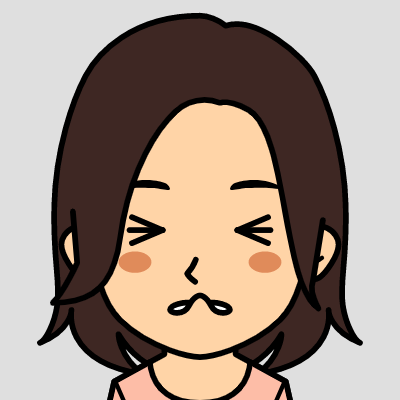
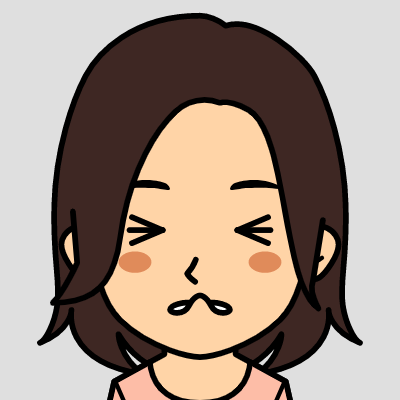
年度によって要件が変わったり、用意する書類が多かったりと確認事項がとにかく多いのです。
そのため、専門分野である社労士が助成金申請をお手伝いします。
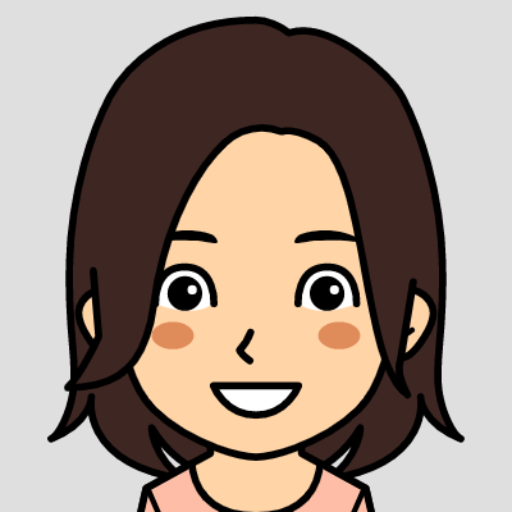
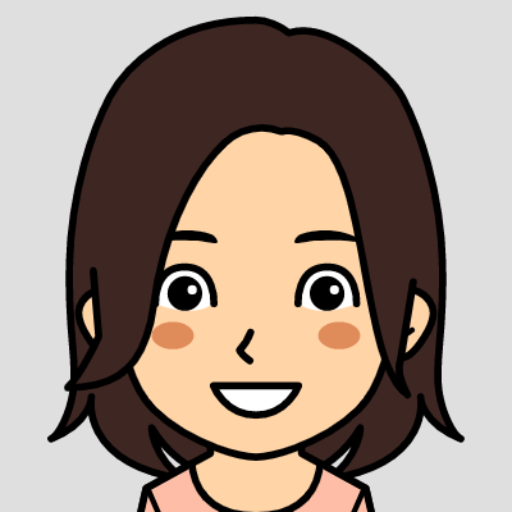
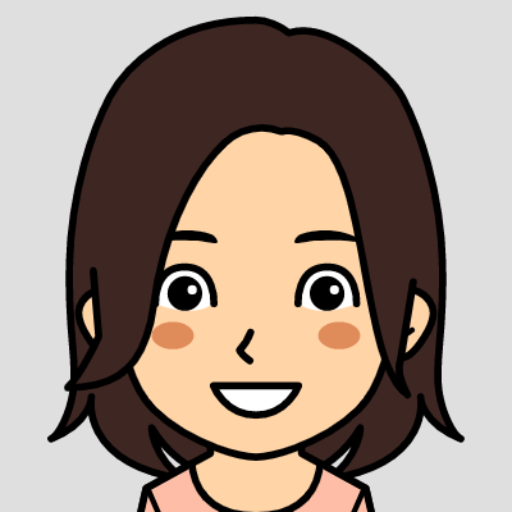
助成金の数はとても多いので、助成金を専門とする社労士事務所もあります。
ちなみに、厚生労働省が行う助成金だけではなく、各都道府県の労働基準監督署が運営する助成金もあり、正直全てを把握するのは至難の業です。
日々の仕事はどのような感じか
定期的に顧問先企業へ訪問したりすることもありますが、諸手続きの電子申請が一般化してきているため、割とパソコンに向かって作業することが多いです。
訪問でいえば、顧問先企業以外にはハローワークや労働基準監督署、年金機構へ行くことになります。
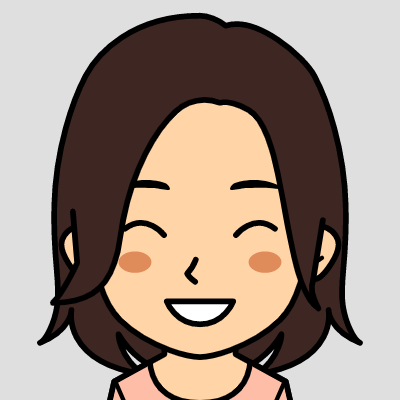
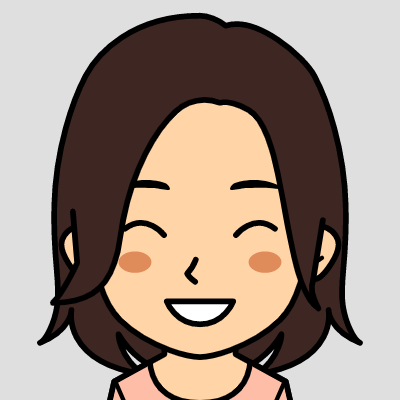
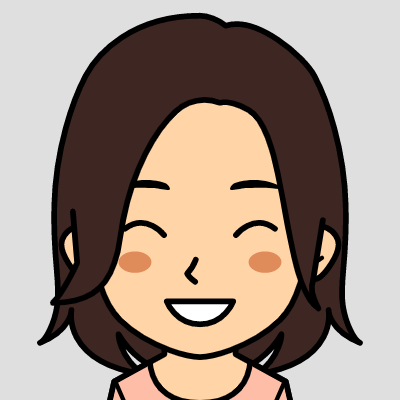
最近は助成金も電子申請や郵送対応してくれる場合も多いため、行く機会は減りつつあります。
就業規則や雇用契約書を考えたり、顧問先企業からの相談の回答を考えたり…考えて文章化することが多いので、ある意味ライティング能力は養われます。
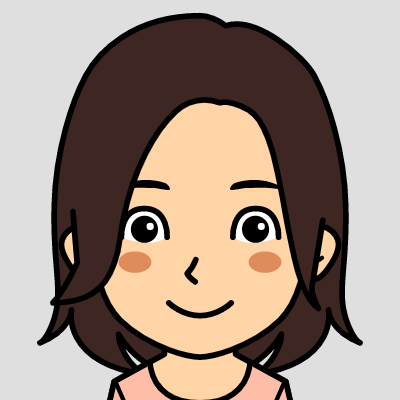
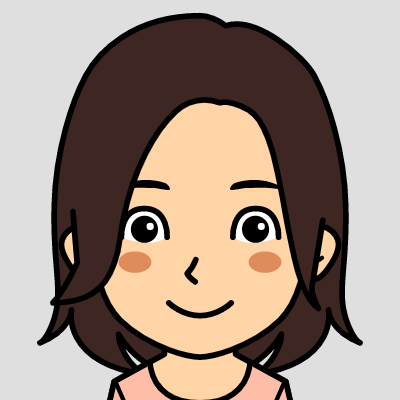
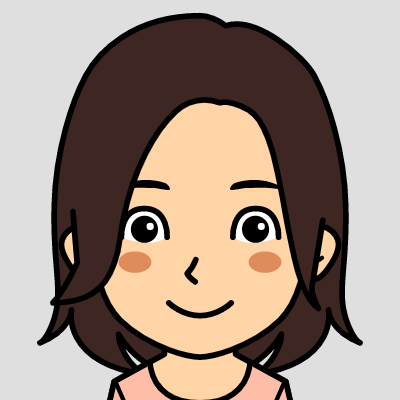
コツコツと仕事をこなすことが好きな方には向いていると思います。
正直…お仕事的には地味なことが多いです(笑)
でも、顧問先企業の縁の下の力持ち的な役割なので、「たくさんの企業の役に立ちたい!!!」という思いがあるとやりがいを感じられると思います。
事務所業務以外のお仕事
社労士としてお仕事をする場合、各都道府県・各市区町村の社会保険労務士会に所属することになります。
定期的に社会保険労務士会から様々な行政協力のお仕事のオファーがあり、参加すると日当がもらえますよ。
内容としては、年金相談や労働保険年度更新時の職員など様々です。
社会保険労務士になったら、こういったことに参加することで経験値を上げることができます。
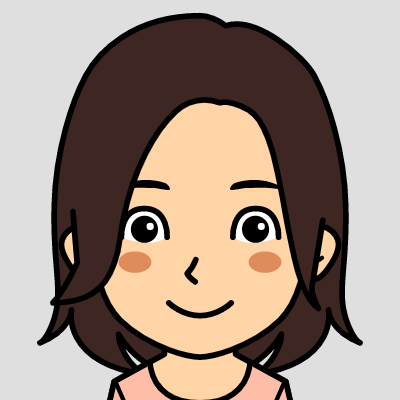
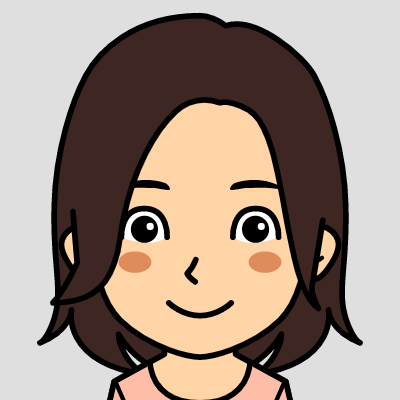
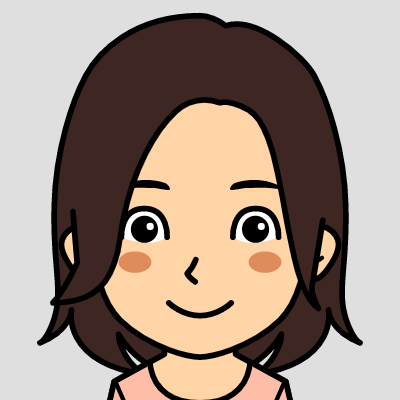
行政協力に参加している他の社労士さんとお知り合いになれたりするので、参考になるお話しが聞けるのは楽しいですよ。
社労士にチャレンジしようかなと思ったら
社会保険労務士試験については以下の記事にまとめているので、是非参考に見てみてください。


社労士になろう!!!と思ったら、通信講座の申込をするのがおすすめです。
👇私が受けた通信講座です
私が受講したフォーサイト以外にも、様々な予備校で社会保険労務士の通信講座が開設されています。
👇TAC
👇LEC
👇ユーキャン
気になった予備校を是非のぞいてみてください!!


独学が良いという方はこちらへ👇